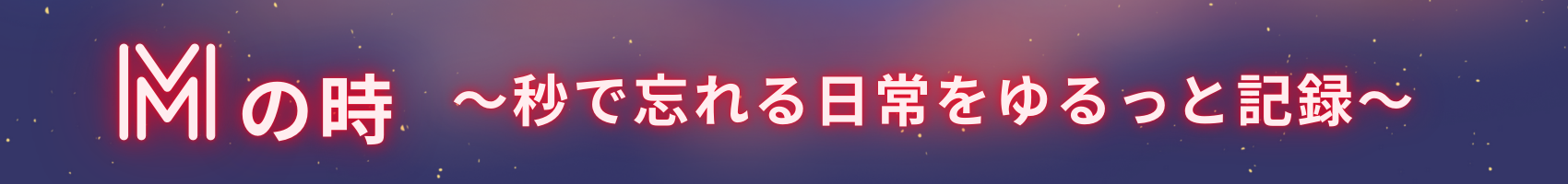2025年秋、日本政治に歴史的転換点が訪れました。
長年続いた自公連立が崩れ、「高市早苗新内閣」が誕生。
そこには、まず「公明党、ついに連立離脱」という衝撃の決断がありました。
さらに迷走気味の「国民民主はどっちつかず?」という姿勢が政局をより複雑にしています。
一方、政界を揺るがせたのは「維新との電撃連立」。
大阪発の改革派がついに政権の中枢に入りました。
その背景にあるのが、「『高市カード』切った自民の勝算とは?」という戦略です。
SNS上では「ネットの声は賛否両論」が渦巻き、期待と不安が交錯。
実際には「高市政権が直面する“現実”」も多く、経済・外交・支持率と課題は山積みです。
それでも日本は新しいリーダーとともに動き始めた。
「それでも前へ?」——令和の政治は、予想を超えたドラマの連続です。
公明党、ついに連立離脱 “駆け引きの限界”を超えた瞬間
1999年の連立開始から約四半世紀。自民党と公明党は“持ちつ持たれつ”の関係を続けてきた。
しかし、近年の防衛・安保政策をめぐる温度差は限界に達していた。
防衛費増額、敵基地攻撃能力、憲法改正…。自民が「現実主義」に舵を切る一方、公明は“平和の党”としての立場を崩せなかった。
世論調査(NHK・10月初旬)では、公明党の「政府の方向性に賛成」層はわずか23%。支持母体の創価学会内でも「これ以上の妥協は無理」という声が高まっていたという。
最終的に“円満離婚”という建前で幕を閉じたが、実態は感情の行き違いによる“熟年離婚”に近い。
SNSでは「ついに別れた」「長すぎた春」など、まるで芸能ニュースのようなコメントも飛び交った。
国民民主はどっちつかず?「中間の美学」か「存在感の薄さ」か
一方で注目されたのが国民民主党。自民寄りの姿勢を見せながらも決定打を打てず、最終的に“傍観者”として取り残された。
支持率は5%前後で横ばい。ネットでは「政治界の中間管理職」「風見鶏にもほどがある」といった辛辣な声も。
ただし、見方を変えれば「柔軟な中道」という立場を貫いたとも言える。
玉木代表は「対立ではなく対話を」と繰り返し発言しており、これはある意味“理性的な政治家”としての姿勢でもある。
問題は、その理性が有権者の心に届いていないことだろう。政治の世界では、正論よりも“物語”が求められる——このあたりが国民民主の永遠の課題だ。
維新との電撃連立 裏で動いていた“静かな握手”
公明離脱で生まれた“空白”を埋めたのが、日本維新の会だった。
大阪発の改革派がついに国政中枢へ。
表向きは「政策協力」とされるが、水面下ではすでに数か月前から接触があったという。
自民の若手議員いわく、「高市氏の掲げる“行動する保守”と維新の“実行力”は相性が良かった」。
維新にとっても“政権与党入り”は悲願。地方行政で培った改革力を国政に持ち込めるチャンスだ。
ただ、SNSでは「大阪が日本を乗っ取った」「官邸が関西弁になる日も近い」など、半分冗談・半分本気のツッコミも。
「高市カード」切った自民の勝算とは? 保守層再結集のシナリオ
自民党が高市早苗を選んだのは、単なる“女性初の総理”という話題性だけではない。
党内では安倍路線を継ぐ保守層の再結集が狙いとされている。
選挙データを見ても、2024年の統一地方選以降、保守系無党派層の約3割が維新・国民に流れていた。
そこを再び取り戻すための「高市カード」だったのだ。
高市氏自身、政策通としての評価は高い。防衛・経済・外交、どの分野でも“言葉が重い”政治家だ。
ネットでは「やっと本気のリーダーが出てきた」「辛口だけど信頼できる」と肯定的な意見も増えている。
ただ、辛口すぎて“党内の空気がピリつく”という噂もあり、「内閣というよりサバイバルゲーム」との声も。
ネットの声は賛否両論「やっと変わるのか」「また同じか」
X(旧Twitter)上では、#高市内閣 がトレンド入り。
賛否は見事に真っ二つに割れた。
「やっと女性が首相に」「保守だけど期待する」など前向きな声の一方で、「結局は安倍路線の焼き直し」「顔が変わっただけ」との冷ややかな意見も目立つ。
興味深いのは、20〜30代の若年層で支持率がやや高い点(JNN調査では38%が“期待する”と回答)。
政治に対して冷めた世代が“行動力のある女性首相”に関心を示すのは、時代の変化を感じさせる。
もはや“イデオロギー”ではなく“人間としての強さ”が評価される時代なのかもしれない。
高市政権が直面する“現実”——支持率・外交・経済の三重苦
とはいえ、就任直後から課題は山積みだ。
初動の内閣支持率は47%(読売調査)とまずまずだが、経済政策への期待は低く、「物価」「賃上げ」「円安」が三大不安要素。
外交でも、中国・北朝鮮・ロシアと難題が続く。
SNSでは「防衛費より給料上げて」「外交より物価」といった“生活目線”の声が多い。
高市首相がどこまで国民目線に降りてこれるかが、今後の支持率を左右しそうだ。
政治も推し活も、“推し続ける覚悟”が問われる時代である。
それでも前へ?「女性リーダー時代」の幕開けに何を期待するか
世界を見れば、メルケル、トラス、アルデンなど、女性リーダーが一時代を築いた例は多い。
彼女たちに共通していたのは、“芯の強さ”と“現実主義”。
高市首相にもその要素はある。
「信念を曲げない頑固さ」は、時に批判を呼ぶが、政治に必要な“安定軸”とも言える。
世論は冷静だが、少なくとも“動き始めた日本政治”を感じる人は多い。
「保守と改革」「東京と大阪」「男性政治と女性政治」——その境界が少しずつ溶けていく。
令和の大逆転劇は、まだ幕開けにすぎないのかもしれない。
とうとう高市さんが総理になりましたね。
あの総裁選からここまで、まさにジェットコースターのような道のりでした。
個人的には、公明党の連立離脱は「アリ」どころか「オオアリ」だと思います。むしろ、今まであの組み合わせでやってきたこと自体が奇跡かもしれません。
一方で残念なのが国民民主。
玉木さん、今回は完全に“風見どころか無風”でしたね。
せっかくのチャンスを自らスルーしてしまった感があります。
そして最後に一番おいしいところを持っていったのが維新。
あのタイミングでの連立は、もはや政治版の“逆転サヨナラホームラン”。
いろいろありましたが、ここからが本番。
新内閣にはぜひ、“国民目線の政策”を期待したいところです。