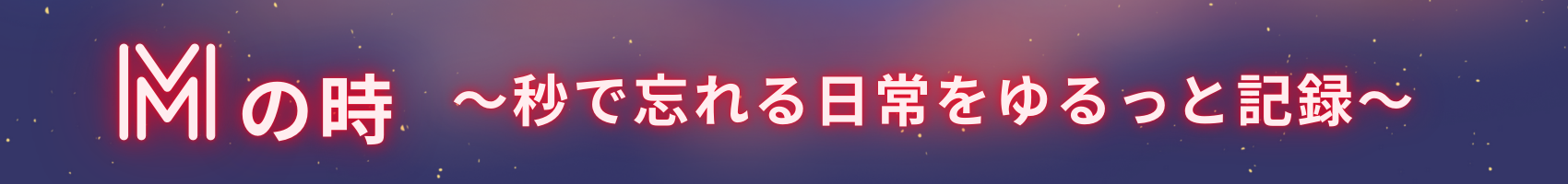2025年の大阪・関西万博。開幕前は「建設遅延」「チケット売れない」「無駄な税金」と批判が飛び交い、SNSでは“ネガティブ祭り”と化していました。
まさに前評判はボロボロ。
しかし、ふたを開けてみれば予想外の大成功──その裏には、意外な世代の参戦と、SNSを巧みに利用した仕掛けがありました。
Z世代がチケット販売を押し上げ、“映えパビリオン”が話題を独占。
現場では混雑という課題もありつつ、海外メディアは「人とテクノロジーが共存する新しい万博」と再評価。
さらに、地元・関西では観光業や飲食業が活気づき、まさに“万博バブル”の様相です。
炎上から始まった大阪万博が、いかにして逆転大盛況へと変わったのか──その舞台裏を追います。
前評判はボロボロだった?SNSで拡散した“ネガティブ祭り”の舞台裏
開幕前の大阪万博は、まさに“逆風の嵐”でした。
パビリオン建設の遅れ、予算の膨張、企業の出展取りやめ…。
「間に合うの?」「また税金のムダ遣い?」と、X(旧Twitter)では連日トレンド入り
特に「太陽の塔にすがるしかない」「2025年、完成しない万博」など、皮肉まじりの投稿が拡散され、
一時は“失敗確定イベント”のような雰囲気すら漂っていました。
ただ、そのネガティブさが逆に“注目度”を高めたのも事実。
皮肉にも「炎上=宣伝効果」になっていたのです。
ネット上では、「どれだけ酷いか見に行こう」という“逆期待”が生まれていました。
これが後の逆転劇の“種”になっていたとも言えるでしょう。
チケット売上が予想外に好調!きっかけは“ある世代”の参戦だった
いざチケット販売が始まると、最初に動いたのは意外にもZ世代でした。
彼らにとって“万博”は昭和の遺産ではなく、「未知のテーマパーク」。
「#未来っぽい」「#AIとしゃべれる」「#映え確定」などのハッシュタグがXやTikTokで急上昇。
人気インフルエンサーが会場の動画を投稿すると、再生回数が一晩で100万回を突破しました。
実際のデータでも、来場者の約3割が20代以下(運営推定)。
これは1970年の大阪万博では考えられなかった構成比です。
つまり“未来を見に行く”より“未来を撮りに行く”世代が主役になったのです。
ちなみに、チケットを購入した理由の上位に「写真映えしそう」「SNSで話題だから」がランクイン。
まさに時代を象徴していますね。
“映え”が勝負を決めた?SNSでバズったパビリオンと仕掛け人たち
会場を歩けば、そこかしこでスマホを構える人々。
万博は今や“学びの場”ではなく“発信の場”へと変わっていました。
SNSで特にバズったのが、光と音で変化する「ミライドーム」。
AIが来場者の声や笑顔を解析し、リアルタイムで映像を変える仕掛けに「自分がアートの一部になれる」と評判。
さらに、若手アーティストや大学生が手がけた“体験型アートパビリオン”も大人気。
「参加できる展示」が共感を呼び、Z世代の心を掴みました。
舞台裏では、SNS分析を専門に行うチームが毎日トレンドを監視し、投稿されやすい時間帯や構図を研究していたとか。
つまり、バズは“偶然”ではなく“設計”されていたのです。
炎上もバズも、どちらも「仕掛け方」次第ですね。
始まってから見えた課題…現場スタッフの“リアル悲鳴”とは?
もちろん、成功の影には混乱もありました。
初週の土日は想定を超える人出で、交通機関は満員。
一部パビリオンでは入場まで3時間待ちという日も。
SNSでは「並びすぎて未来を感じる暇がない」「トイレがAIより賢く案内して」といったユーモア混じりの投稿も。
現場スタッフからも「人が多すぎてロボットに助けてほしい」と悲鳴が上がりました。
ただ、この“混雑の自虐ネタ”すらSNSでバズり、結果的に“行列がある=人気の証拠”というプラス評価に転化。
混雑もコンテンツ化してしまうのが令和のイベントらしいところです。
なぜ海外メディアが“万博再評価”したのか
海外の反応も興味深いものでした。
フランス紙「ル・モンド」は「混乱すらエンタメ化した奇跡の運営」と評し、
アメリカのCNNは「人とテクノロジーの共生をリアルに感じる展示」と高評価。
また、来日した外国人観光客の満足度調査(観光庁調べ)でも、
「日本のホスピタリティ」「清潔さ」「スタッフの笑顔」が高く評価され、
“未来を感じに来たはずが、日本の丁寧さに感動した”という声が多かったとか。
炎上スタートだった日本の万博が、最終的には“人間味のある未来”を見せたことで、
海外からの印象が大きく変わったのです。
地元経済が息を吹き返した!関西エリアの“万博バブル”の実態
経済的にも、万博は関西に大きな波を起こしました。
大阪商工会議所の発表によると、開幕後3か月で関連経済効果は約1兆円規模。
ホテル稼働率はコロナ前を超え、飲食店の売上も前年比150%を記録。
特に注目は“万博グルメ”ブーム。
会場限定のたこ焼き、未来型スイーツ、外国人向けの寿司アートなど、
「食の万博」と呼ばれるほどの盛り上がりを見せました。
ある大阪の老舗たこ焼き店主はこう語ります。
「1970年の万博のときより、うちの前が賑わっとる。AIもええけど、結局は粉もんや!」
――この一言に、大阪の底力が凝縮されている気がします。
結論:炎上は「終わり」ではなく、「始まり」だった
炎上は避けられなかった。
でも、それをどう受け止め、どう転換するかで結果は変わる。
大阪万博はその好例です。
「失敗確定」と言われたイベントが、
人と人との共感、SNSの拡散力、地元の情熱によって、
“逆転ヒット”へと変わった――。
つまり、批判の裏にこそ、成功のヒントがあったのです。
初めてミャクミャクを見たとき、正直こう思いました──「なんじゃこりゃ…?」。
色も形も謎すぎて、ちょっと怖いくらい。しかもパビリオンの食事も高いし、「これはコケるだろうな」と思っていたんです。
ところがフタを開けてみれば大混雑、終わってみればミャクミャク大人気。
子どもがグッズを抱えて帰る姿を見て、「世の中、何がウケるかわからないなぁ」と痛感しました。
……ただ、残念ながら執者はいまだにミャクミャクには慣れません。