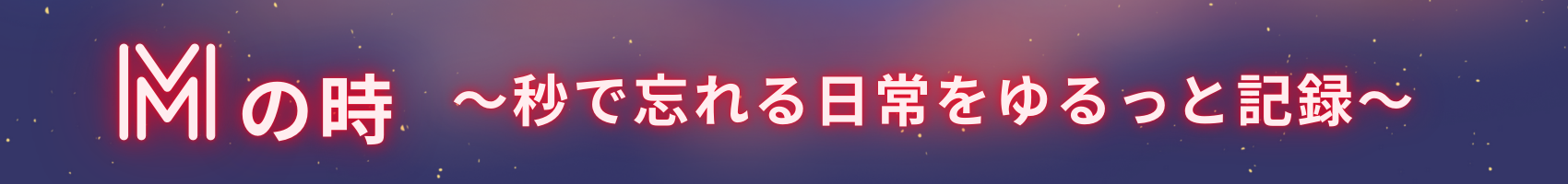2025年ノーベル化学賞を受賞したのは、京都大学名誉教授の北川進氏。
彼が生み出したのは、CO₂などの気体を自在に分離・貯蔵できる“魔法の金属”──多孔性金属錯体(PCP)です。
本記事では、北川氏の経歴や研究の原点から、PCPの仕組み、CO₂を捕まえる最新技術、ノーベル賞受賞の理由、そして未来への応用までをわかりやすく解説します。
さらに、北川氏の研究哲学や日本人ノーベル賞の流れにも触れ、科学の魅力と可能性を深掘りします。
北川進氏とは?
2025年、ノーベル化学賞のニュースが日本中を駆け巡りました。
受賞者は京都大学名誉教授の北川進(きたがわ すすむ)氏。
「また日本人が!」と歓喜する声が上がる一方、「北川さんって何をした人?」という声も少なくありません。
北川氏は、長年にわたり分子レベルでの物質設計を研究してきた化学者です。
研究者仲間からは“分子の建築家”と呼ばれることも。
学生時代から「見えないものを作る」ことに魅せられ、実験室で分子の“家”を組み立ててきました。
その成果が、今回のノーベル賞受賞につながった多孔性金属錯体(PCP)の開発です。
「多孔性金属錯体(PCP)」とは?
「多孔性金属錯体」…なんだか舌をかみそうな名前ですよね。
簡単に言うと、金属と有機分子を組み合わせて作った“穴だらけの物質”です。
英語では「Porous Coordination Polymer」、略してPCPと呼ばれます。
この物質、実はすごい特技を持っています。
その無数の微細な穴(ナノサイズ)が、まるでスポンジのようにガス分子を吸着・分離できるんです。
CO₂(二酸化炭素)やメタン、アンモニアなど、分子ごとに“選んで捕まえる”ことができる。
つまり、空気の中の成分を自在に整理整頓できる“分子の整理整頓係”のような存在です。
北川氏がこの構造を初めて発表したのは1990年代後半。
当時は「そんなもの作れるはずがない」と言われましたが、見事に成功。
今では世界中の研究者が追随し、新しい分離技術・貯蔵技術の基盤となっています。
CO₂を“捕まえる”技術が注目される理由
では、なぜこの研究がノーベル賞につながったのか?
答えはズバリ、「地球温暖化対策への貢献」です。
いま世界が直面している最大の課題の一つが二酸化炭素(CO₂)の排出削減。
石炭火力発電や工場、車などから出るCO₂を減らすには、“排出しない技術”と同じくらい、“出たCO₂をどう処理するか”が重要です。
ここで登場するのがPCP。
PCPは、CO₂だけを選んで吸着する特性を持つため、排気ガスの中からCO₂を効率的に取り出せます。
しかも、一度吸着したCO₂を再利用可能な形で取り出すこともできる。
要するに、「出てしまったCO₂をリサイクルできる」という夢のような素材なのです。
北川氏自身も「CO₂を敵ではなく、資源として使える時代が来る」と語っています。
地球規模の問題に対して、分子レベルの発想で挑んだ功績──これこそが、ノーベル賞にふさわしい理由です。
ノーベル賞受賞の理由
ノーベル化学賞は、単に難しい実験に成功した人が選ばれるわけではありません。
「人類に貢献した科学」であることが大きな基準になります。
今回の受賞理由には、こう記されています。
“北川進氏は、分子を自在に組み合わせることで、社会課題の解決につながる新たな物質設計の道を開いた”
つまり、PCPは単なる研究成果ではなく、社会を動かす技術と認められたのです。
ちなみに、化学賞の審査はとても時間がかかります。
候補者リストには10年以上前から北川氏の名前が挙がっていたとも言われています。
長年の努力がようやく報われた、まさに「科学者の執念の結晶」といえるでしょう。
PCPが広げる未来
PCPの応用はCO₂だけではありません。
近年は水素社会の実現にも欠かせない素材として注目されています。
例えば、水素を高圧で貯蔵するには危険が伴いますが、PCPを使えば低圧でも安全に貯蔵可能。
また、メタンやアンモニアなど他の気体も、サイズや性質によって“選択的に”吸着できます。
まさに、「空気の中の分子を自由に選べる」時代が見えてきたのです。
国内外の企業もこの技術に注目しており、住友化学やトヨタなどが関連分野の研究を進めています。
もしかすると近い将来、PCPを使ったエコカーや発電システムが登場するかもしれません。
北川進氏の“研究哲学”に学ぶ
北川氏の講演ではよく、こんな話が出てきます。
「発想のきっかけは、同僚との雑談からだった」
どうやら、コーヒー片手にした会話の中で、「分子を積み木みたいに組めたら面白いね」というアイデアが生まれたそうです。
つまり、革新的な科学も、最初は“何気ない一言”から始まる。
これ、日常生活にも通じますね。
「無駄話も時には宝になる」──そんなメッセージを感じます。
学生たちにも「失敗を恐れず、遊び心を忘れないように」と語る北川氏。
研究室では、実験の合間に雑談と笑い声が絶えなかったとか。
硬派な科学の世界にも、ユーモアが必要なんですね。
余談:日本人ノーベル賞受賞ラッシュ、次は誰?
日本人のノーベル賞受賞はこれで29人目。
近年は化学賞の受賞が多く、「日本の化学力」が改めて世界に知られる形となりました。
過去には白川英樹氏(導電性高分子)、根岸英一氏(有機合成反応)、吉野彰氏(リチウムイオン電池)など、生活に直結する発明が評価されています。
今年の北川氏もまさにその系譜。
「実験室から地球を救う」──これほどロマンのある話はありません。
来年は誰が受賞するのか。
個人的には、AIや再生医療の分野からも日本人が登場しそうな予感です。
科学の進歩は止まりませんね。
「雑談からノーベル賞」――そう聞くと、ちょっと勇気が出ますよね。
実はこのブログも、“雑談のネタになれば”という思いで書いています。
とはいえ、高尚な研究のように世界を変える話ではなく、「沈黙が続くあの空気をどうにかしたい…!」という、もっと生活密着型の動機です。
ニュースの裏側やちょっとした小話が、会話のきっかけになれば十分。
もし読んでクスッと笑えたなら、それも立派な「雑談発の小さな発見」かもしれません。